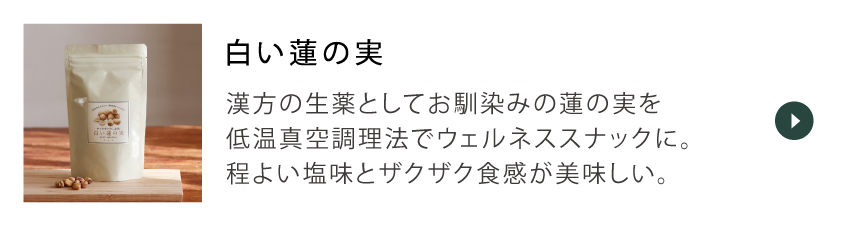沖縄の自然と風土を活かし、農薬を使用しない約4万坪の広大な農園で様々な薬草、植物を育てる傍ら、産学連携による研究開発やエビデンス取得など、人々の健康に寄与するものづくりや健康食品製造に心血を注いでいる沖縄長生薬草本社。
10年以上に渡り、黒人参茶やゴールデンラテ、SAKEKINGなどの製品開発や沖縄のハーブや植物をはじめ、植物原料の提供でお世話になっている下地会長にお話をうかがいました。
<プロフィール>
(有)沖縄長生薬草本社 代表取締役会長 薬学博士 下地清吉さん
幼少期の体験を活かし、20代から本格的に薬草の研究に没頭。
1974年に法人化し、以来50余年に渡り薬草の栽培と研究、商品化に取り組んできた。
2003年に農事生産法人沖縄長寿薬草組合を設立。2005年農林水産杯天皇杯受賞。2012年秋ウコンの品種改良により生まれた沖縄皇金を品種登録。2022年より代表取締役会長に就任。
CONTENTS
自然と向き合うことで恵みを活かす。
60余年の薬草作りで培ってきた経験
── ここに来る度に感じますが、今日もすごくいい香りがしますね。
(下地会長)ああ、それ、そこ(隣の工場)でハーブやウコンを乾燥してるからね。乾燥している植物の種類によって香りが違うから、毎日香りが違うね。
ここに居ると乾燥しているハーブや育てているハーブの香りが届いてね。
風の向きとかでも変わるから面白いよ。
今日は黒人参やっとるなーとか長命草やっとるなーとか、歩くだけでわかるよね。

台風は、沖縄を育てる”自然の恵み”
── 黒人参茶を始める前からのお付き合いも、気づけばもう10年以上となります。
これまで会長にも何度もお話を伺ったり、畑や工場を一緒に回らせていただきましたが、改めて「土壌」や「生産環境」についての特徴やこだわりを教えていただけますか?
(会長補佐・林さん)やっぱり会長が一番こだわっているのは、土づくりですね。土が良くないと立派な植物は育たないですから。
(下地会長)そう、土もそうだけど、気候も大きいね。沖縄本島でも北部と南部で土が違うんだけど、それ以上に、亜熱帯の気候ってのが大きい。
とはいえ、「亜熱帯だからみんな良い」というわけではなくて、沖縄ならではの特殊な要素―微粒子、塩分、サンゴ礁由来のミネラルなど、自然環境が複雑に絡み合っているから、その環境に向き合って育てているっていうのが一番のこだわりかも。
例えば、毎年来る台風。
もう60年以上やってきてるから、花の色や咲き具合を見れば、「今年は台風が強いな」「たくさん来るな」とか分かるくらい。やっぱり台風にも自然の法則みたいなものがあって「沢山発生するけど、今年は来ないな」ってときにはさーっと素通りしていったり、逸れていったり。
毎日畑に出て植物を見てたらわかる。
ちょっと話が逸れたけど、台風と言えば災害のイメージがあるけど、そうじゃないね。
必要な自然のサイクルのひとつでその自然のサイクルが植物の育ち方に影響していて、害虫を吹き飛ばしてくれたり、微粒子やミネラルを運んできたりする。それが結果的に栄養素の違いや、抗酸化作用の強さにつながっているんだと思うね。
実際に富山大学や東京大学で調査してもらった結果、沖縄産の植物は栄養素の質が違うというデータがしっかり出てる。
海外産も含めて、同じ植物の平均的なデータと照らし合わせてみたけれど、やっぱり違う。マレーシア、タイ、台湾、インドとか他の亜熱帯・熱帯の環境で採れた植物とも比較したけど、やっぱり違う。
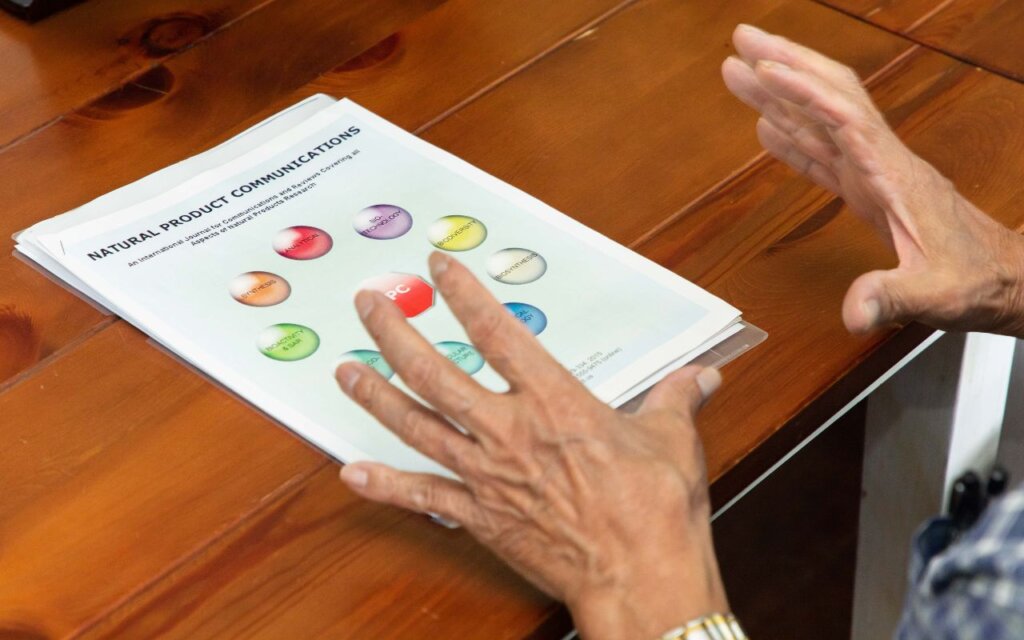
――気候、土、作り方。それぞれが影響しているんですね。
(下地会長)もしかしたら私が作っているからかもしれないけど…
これは冗談ね(笑)
ただね、その栄養だったり身体への影響だったりを「食べる人」にもきちんと伝えていかなきゃいけない。薬草に詳しい人はたくさんいるけれど、毎年毎年データを記録して、自然環境に応じて「この気候ならこう育てるべき」とか、「ここで取れたやつはこんな栄養がある」とか、そんなところまで考えている人は本当に少ないね。
逆にそんなことをしてるから、自分なりに「今日収穫しないと」「明日じゃないと」とか、毎日畑を巡回しながら気づくわけで、それを逃したらダメなんだけど、なかなかみんなはそうはいかんね。
まあ、これをね、どう伝えていくかは難しいところで、本にしたり、大学と一緒に研究結果として残そうとしてるけど…
色んなところから畑を見に来る人も多くて、説明対応したりするのは私しかできないから、結構忙しくてなかなか本作りも進まないね。

安心・安全は栽培から製造まで
── 製造環境についてはいかがですか?GMPやISOなど、品質管理も徹底されていますよね。
(林さん)最初にISO9001を取った時はHACCPも同時に取得したので、結構大変だったのは覚えていますが、かなり前(2003年)なのでちょっと記憶が曖昧ですね(笑)。
2018年にISO22000※を取得したときのことはよく覚えています。
普通は「工場単体」で認証を取るところが多いけど、うちは「土づくりを含めた生産全体」で認証を取ったんです。これはかなり珍しいことだと思います。
※ISO22000:食品安全マネジメントシステムに関する国際規格
―― そこは大きなポイントですよね。
(林さん)「安全なものを届けたい」「薬草の力を正しく届けたい」―そう考えると、やっぱり工場だけやっても意味がないというか足りないですよね。
(下地会長)あとで一緒に工場も回るけど、土から育てて、収穫して、そこ(隣の工場)で加工して、全部見えるからね。作り方や土、環境で栄養も変わってくるから、全部やらないと。
農薬を使わずに土を育てて、自然の恵みをいただいてね、安全で身体に良い薬草を育てても、製品にするところがしっかりしてないともちろんダメだし、製造も機械がだいたいやってくれるけど、ちゃんと人の眼で見てやらないとダメだね。

春ウコン(キョウオウ)の可能性
── では、ウコンについても少し。御社では酒豪伝説をはじめ秋ウコンの新品種「沖縄皇金(おきなわおうごん)」を結構前面に出してきましたが、個人的には春ウコンの薬効にもとても魅力を感じています。春ウコンの特徴について教えてください。
(下地会長)うん、春ウコンに大きな可能性を感じているのは一緒だね。
(林さん)春ウコンはSAKEKINGにも入れてますよね。
──はい。メイン素材として入れてますね。
(下地会長)春ウコンは元々は宮古島で採れていて、昔は宮古島じゃないとほとんど育たなかった。石垣島だと白ウコン、本島だと秋ウコンが中心。今はみんな育て方がわかってきて色々なところで育てているけど、やっぱりその土地が持つ土や気候と関係するんだろうと思う。
でも、春ウコンは原産地が不明で、現在でも宮古なのか大陸なのかははっきりしてない。まあ、これを調べようと思ったら、人骨とか化石とか考古学の世界も絡んでくるし、とてつもない時間と労力が掛かると思うけど、少なくとも古くから宮古島で採れていたというのは確認されている。
栄養成分の面で言うと、秋ウコンよりも圧倒的にミネラルやフラボノイドが多くて、胃腸によかったり、抗酸化力が高かったり、あとは血圧にもいいね。クルクミンががんに良いというのは結構前から研究結果として発表されてるけど、春ウコンもね、知り合いの統合医療の先生が研究してくれて、がん細胞の死滅効果が報告されたり、免疫系や認知症に対する研究が進んだりと、非常に期待されてるね。
あとは通常、植物に限らず何でもそうかもしれないけど、摂りすぎると副作用が出ることがあるけれど、春ウコンはそうした副作用が見当たらない、というのも大きな特徴かもしれないね。

── 元々、古くから生薬としても使われてきたわけですが、現代医学の世界でも色々と成果が見えてきたというのはこれからが楽しみですね
(下地会長)うん、春ウコンの薬効はこれからもっとわかってくると思う。沖縄皇金は約25年かけて研究してきたけど、春ウコンもあと10年くらいかけてじっくり取り組む必要がありそうだね。
何百年、何千年と生薬として、民間薬として使われてきたことを考えれば短いけどね。
沖縄皇金の時は、糸を引く根茎を見て、納豆菌のような脂肪燃焼や代謝促進作用があるんじゃないかと思ったのが研究のきっかけで、誰もそんなところは見てなかったからそこから時間が掛かったけど。
その時と比べたら、春ウコンは大学から調査依頼や協力の話がたくさん来ているし、すでにある程度わかってきてるから。まあ、もうちょっと時間はかかると思うけどね。
たくさん私たちも試してきたし、色々な文献や研究結果が出てきてるけど、まだまだ健康面で可能性を秘めた植物であることは間違いないね。

まだまだ研究の余地がある薬草の世界
── 春ウコンのエビデンスについてはすごく興味深いですね。
ところで最近では、さし草やクミスクチン、クワンソウなどといった沖縄の植物を使った製品を目にすることが増えてきましたが、新たに注目している薬草はありますか?
(下地会長)長命草、モリンガ、秋ウコンとかはだいぶもう出てるからね…
注目しているというか、問い合わせが多いのは、クワンソウ、クミスクチン、よもぎとかね。
最近はよもぎ蒸しの材料とかで問い合わせが多いね。
フーチバー(にしよもぎ)は、沖縄だとそばに入れたり、煮物に入れたりして使われてるけど、血圧、腎臓、糖尿病など、幅広い効果があるのはかなり前からわかってるよね。昔からケガしたらよもぎを塗ったりしてたけど、抗菌作用だけじゃないよね。マンジェリコンも糖尿病関連で注目しているし、まだまだ研究の余地があるものが沢山あるね。
黒人参もあなた達が大学で試験したとおり、抗酸化機能が高いだけじゃなく、血管とかにも良いだろうし、もっと広がるんじゃないかなと思っている。普通に食べても美味しいしね。あとで畑で抜いたらいいさ。
黒人参をね、お酒に浸けるともう2~3日で赤ワインが出来上がる(笑)。
ポリフェノールも赤ワインの何倍も入ってるし、飲みやすくて身体にも良いお酒ができる。
── 以前、泡盛とラムにそれぞれ浸けてみましたが甘味があって美味しかったですね
(下地会長)人参が甘いから、美味しいのができる。
あとで抜いたやつを泡盛と一緒に持って帰って浸けたらいいよ(笑)。

古来より人間が身体で感じてきた薬草の魅力
(下地会長)植物の効能という点では、植物には古い言い伝えがたくさんあって、それを辿っていくと面白い。
よもぎ蒸しが最近流行ってるって言ったけど、よもぎの香りが身体を元気にする、という話は今に始まったことじゃなく古くからあって、昔の人が自分の身体で感じて学び、自然の力をうまく活用していたことがわかるよね。
よもぎはね、香りだけで解毒だったり、健康的な効能があるって言われているけど、やっぱりそこには由来があってね。
ある大金持ちの男が貧乏な家の娘を嫁にもらった。
そして贅沢な生活していくわけだけど、この娘が病気にかかってしまった。
で、このまま死んでいくよりは田舎に返してしまおうとなり、娘は息絶え絶えになりながら、何日もかけて田舎に帰っていった。
その道中で何度も休憩しながら帰るわけだけど、よもぎの葉を被って寝て、歩いて、って繰り返しているうちに、田舎に辿り着くころにはすっかり元気になっていた。
という話なんだけど、香りがね、身体の中に入って元気にしてくれるっていうのは今のよもぎ蒸しとかにも繋がる話なんじゃないかなと。
こんな由来がたくさんの植物にあって、長命草もそうだし、黒人参もそうだし、調べてみると良いよ。沖縄独自のものもあるし、日本だけじゃなく海外にも沢山ある。
よもぎに関しては韓国の文献でも沖縄のよもぎの効能について触れてるものもあって、結構韓国からの問い合わせも多いね。
── フーチバーは、ハママーチではなく「にしよもぎ」ですよね。
(下地会長)そう、琉球よもぎ(ハママーチ)ではなく、にしよもぎ。沖縄では間違えて呼ばれることも多いけど、にしよもぎの方が薬効が高いね。
薬草だから何でも良いわけではなくて、あまり良くないというか、使い方次第では良くないものもある。名前が似てるものもあるし、結構間違えて使ってることもあるから、ちゃんと研究して使っていかないと。
昔ね、ウコンが良いって言って色んな会社が出したりしたけど、ウコンだけでも数10種類あるし、同じウコンって名前がついてても植物の分類が違ったり、当然栄養や効能も違うわけだしね。
今後は「植物から入る」のではなく、中の成分とかデータを見て「病気や健康のために植物を選ぶ」というのが増えるだろうね。
長命草が良い、ピパーチ(ヒハツ)が良いではなく、不整脈だったり、糖尿病だったり、そういうのにこういう成分が効くから、ここのこの薬草がという風にね。

── 最後に、これからの取り組みについて一言お願いします
(下地会長)まだまだ魅力がある薬草がたくさんあるし、研究が進んでいないものが多い。
そういうのをね、どんどん研究して健康に活かす。
これまで60~70年と薬草作りと研究をしてきたわけだけど、こうやって伝えるのは私しかできないから、できるだけ沢山の人に伝えてね。今も本を作っているけどね。
忙しいけど、春ウコンもそうだし、接骨草もそうだし、マンジェリコンも…もっと研究して、データにしてちゃんと残していきたいね。
そういうのを広めていくのを社長たちにはもっとやって欲しいし、もっと一緒に開発を進めてほしいね。もうちょっと沖縄に来んといかんね(笑)
今度、宮古に新しい畑を準備しているから、そこも一緒に来てもらってね。
美容もそうだし、リラックスとか精神的なところもそうだけど、社長のところ(リフェット)はそういうの得意だよね。薬草の成分だったり、どのくらい摂ると良いってのは、うちの石川(専務)も詳しいから、女性向け商品のノウハウも活かして、「どんな問題を解決したいか」というところから色々な薬草を一緒に研究してね、どんどん健康に役立つ新しい商品を作っていってほしいね。
── ありがとうございました!

- Editor’s Note -
共同での商品開発や当社製品の製造など、長きに渡ってご協力いただいている長生薬草本社。
会長を見習ってではないですが、訪れるたびに畑や農園を歩くことが習慣化しており、鬱蒼と生い茂る植物に囲まれる時間は、仕事でありながらもエネルギーをもらい、そしてどこか癒しを感じる時間になっています。
海風、土、植物の香り、のんびりとした空気の中にどこか厳かな雰囲気があり、リゾートエリアとは異なる沖縄の魅力を感じさせてくれる南部エリア。
旅行で沖縄に訪れた際に、南部まで足を延ばすという方は少ないでしょうが、実は史跡も多く、沖縄の自然を感じたい、何もしない旅をしたいという方にはおすすめのエリアでもあります。
近いうちに長生薬草本社に併設のカフェレストランが再オープンする予定もあるそうなので、ぜひその際はハーブの力と美味しさを体感しに訪れてみてください。
(おすすめは朝採れハーブのしゃぶしゃぶです)
《インタビュー中に出てきた薬草》

〇ニシヨモギ(フーチバー)
沖縄の古い言葉で「病気」や「薬」を意味する「フーチ」と「葉」を意味する「バー」を合わせた名で呼ばれ、古くから食材や民間薬として利用されてきた。タンパク質や食物繊維、ミネラル、ビタミンが豊富で、成分として含まれる「クロロフィル」には消臭や殺菌作用、悪玉コレステロールなどの有害物を除去する効果があるといわれている。

〇長命草(サクナ)
海水や潮風など厳しい自然環境下で育つセリ科の植物。ポリフェノールやビタミンA,C,E、鉄分、カロテンなどの栄養素が豊富且つバランス良く、高い抗酸化作用や美肌、血流改善など様々な健康効果が期待される。「1株食べると1日長生きできる」と言い伝えられ、古くから長寿に繋がる薬草として親しまれてきた。

〇黒人参
中央アジアやヒマラヤ近隣が原産地とされ、人参の起源種のひとつとも言われる希少なスーパーフード。エイジングの代名詞ポリフェノール(アントシアニン)を豊富に含み、その抗酸化力はブルーベリーの17倍、赤ワインの約22倍。ビタミン類やβカロテン、亜鉛、鉄なども含み、その栄養価の高さからトルコでは黒人参などを乳酸発酵させたジュースが愛飲されている。
《今回訪問したのは…》
(有)沖縄長生薬草本社
https://www.cho-sei.co.jp/
1974年創業、「薬草を源に、人類の健康の為に技術と真心で奉仕する。」を経営理念とし、ウコンや沖縄の薬草を中心とした栽培、健康食品のOEM・PB製造などを手掛け、琉球酒豪伝説や福寿来などお馴染みの商品も多数開発。
沖縄本島、宮古島に所有する約40,000坪の農園は全て農薬を使わず、沖縄の自然と風土を活かした薬草・製品作りに取り組んでいる。

リフェット代表取締役 福岡県出身。自ら足を運び自らの眼で見ることを大切に、邪魔なくらい現場に出てくる代表。両親、祖父母の影響からか幼少期から食や健康への興味が強く、一時期は料理人を志すも現在は美味しい食事・お酒を楽しむ方に。小学生~大学までバスケ、現在は柔術にハマり身体を労わっているのか痛めているのかわからない日々。自然に帰すと子供より楽しんでいる2児の父。